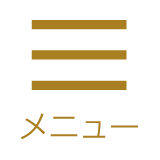歯医者で行っている予防歯科ってどんなの?現役の歯科医が解説します

「歯医者は痛くなってから行く場所」
そんなイメージは、もう古い時代のものになりつつあります。
現在の歯科医療では、むし歯や歯周病になる前に予防することが主流になってきています。
早期発見・早期介入はもちろん、そもそも病気にならないお口づくりが目的です。
ここでは、歯科医院で実際に行われている予防歯科メニューを、現役歯科医の視点からわかりやすく解説します。
予防歯科をする目的とメリット
予防歯科を行う目的
予防歯科の一番の目的は、「生涯、自分の歯で美味しく食事ができるようにすること」。
このために、次の良い状態を維持します。
- 歯周組織の健康
- むし歯の発生抑制
- お口の清潔環境維持
- 口臭予防
- 全身疾患リスクの軽減
など「削る・抜く」ではなく「守る・残す」医療にシフトしているのが現代の歯科です。
予防歯科を行うメリット
①むし歯・歯周病を未然に防げる
病気が進んでから治すより、何倍も楽で安心です。
痛みも負担もありません。
②重症化による治療費が大きく減る
進行したむし歯や歯周病の治療は、被せ物・根管治療・抜歯・インプラントなど、高額になります。
病気になる前に予防することでこれらの治療に係る費用を抑えることができます。
③麻酔や痛みを伴う治療が減る
予防中心に通院している患者さんは、そもそも治療をしないので「痛い体験」が圧倒的に少ない傾向にあります。
④歯ぐきが引き締まり、口臭予防にも
歯周病菌と歯石が減り、口臭改善効果も見込めます。
⑤見た目の美しさが続く
歯面の着色を落とすことができるため、病気の予防だけでなく清潔感も高まります。
⑥将来自分の歯が残る確率が上がる
統計的にも、定期検診を受ける人の方が残存歯数が多いことが証明されています。
歯が多く残ることで、老後の生活の質(QOL)が大きく変わります。
⑦全身の健康に繋がる
歯周病菌は、糖尿病悪化、心疾患、動脈硬化、誤嚥性肺炎など全身疾患と関連があることが報告されています。
お口は健康の入り口と言えます。
歯医者で行っている予防歯科とは
予防歯科とは、むし歯や歯周病になってから治療するのではなく、「痛くなったら治療」ではなく、“病気を未然に防ぐ”ために行う歯科医療のことです。
「痛くならない仕組みづくり」をするのが現代の歯科スタイルになっています。
お口の中のトラブルは、早期発見・早期予防が何より重要です。
歯医者では、以下のような予防処置を行っています。
①歯周病検査やむし歯チェックなどの定期健診
病気は症状が出る前に見つけるのが最も重要です。
定期検診では、歯周ポケットの深さ、歯ぐきの腫れ・出血、歯石の付着状況、噛み合わせ、むし歯の初期サイン、セラミック/銀歯の劣化のチェックを行います。
定期検査を行うメリット
- 早期発見で治療が軽く済む
- 痛みが出ない段階で対応可能
- 歯の寿命が伸びる
目に見えない変化こそ、定期健診で見つかります。
②歯石除去(スケーリング&ルートプレーニング)
歯垢が固まってできた歯石は、ブラッシングでは取れません。
歯科医院では、超音波スケーラーや手用スケーラーを使い、歯石を歯ぐきの上・中両方から除去します。
歯石除去のメリット
- 歯周病の進行予防
- 歯ぐきの出血・腫れ改善
- 口臭軽減
特に見えない歯周ポケットの歯石除去はプロだからこそできる重要処置です。
③プロフェッショナルクリーニング(PMTC)
普段の歯磨きでは落としきれない汚れや着色(ステイン)を、専用の器具と研磨ペーストを使って徹底的に除去します。
PMTCのメリット
- 表面の細菌バイオフィルムを除去
- 歯の表面がツルツルになり汚れが付きにくい
- 口臭予防
- 見た目の清潔感UP
特に、コーヒー・紅茶・タバコの着色が気になる方におすすめです。
④フッ素塗布(歯の強化ケア)
フッ素は、歯の表面を強化しむし歯菌に溶けにくくする効果があります。
フッ素の主なメリット
- 歯の再石灰化を促進
- エナメル質を強くする
- むし歯菌の働きを抑える
特に、子ども、むし歯が多い方、歯並びで磨き残しが出やすい方におすすめです。
⑤生活習慣(食習慣)指導
むし歯や歯周病には、食習慣が大きく影響します。
歯科医院で行う指導は、
- 間食のタイミング
- 糖の摂り方
- 酸性飲料の回避
- スナック菓子の頻度
など、細菌の増殖リスクを下げるアドバイスを行います。
この生活面が改善されると、予防効果をより高くすることができます。
⑥唾液検査(リスク分析)
あなたの「むし歯になりやすい体質」を客観的に評価します。
検査する項目は、
- 唾液の量
- 唾液の質
- むし歯菌の活性度
- 歯に付着しやすい汚れの性質
これらを把握することで、オーダーメイドの予防プランを作成することができます。
⑦歯磨き指導(ブラッシング指導)
「自分はきれいに磨けている」と思っていても、多くの人が磨けていない部位が存在します。
プロから鏡で見ながら、
- 磨けていない場所
- 歯ブラシの角度
- 癖の改善方法
のアドバイスを受けることで、歯周病リスクを下げることができます。
⑧噛みしめ・歯ぎしり(ブラキシズム)対策
無意識の噛みしめは、歯がすり減る、歯が割れる、歯周病が悪化、顎関節症の原因になります。
適切なタイミングで、
- マウスピース(ナイトガード)作成
- 噛みしめ癖の診断
- 顎ストレッチの指導
などを行うことで重症化する前に予防できます。
「歯が欠けた」「急に冷たいものがしみる」人は注意が必要です。
⑨噛み合わせチェック
噛み合わせが悪いと、磨き残しが増える、局所的に負担が集中、歯周病の進行が加速など悪い影響があります。
噛み合わせは咬耗や被せ物のやりかえで変化するため、噛み合わせのチェックは大切になってきます。
⑩口臭検査・口臭カウンセリング
機械やガス解析で科学的に口臭を評価し、口臭の原因が歯周病によるものか、舌苔によるものか、はたまた気のせいなのかを特定することができます。
⑪喫煙者向け歯周ケア
タバコには
- 血流低下
- 炎症増強
- 免疫低下
など、歯周病悪化因子が多いです。
禁煙サポートや、喫煙環境に合わせた口腔衛生指導を受けることで適切な普段のブラッシングケアが可能になります。
⑫矯正相談(歯並びチェック)
歯並びは清掃性に直結します。
悪い歯並びは、
- 磨き残し増加
- 虫歯発生率の向上
- 歯周病悪化
など、審美性の面だけではなく口腔内の疾病の罹患に大きく関わってくるため、早期介入をお勧めします。
予防歯科の治療が台無しになってしまうNGな行動
予防歯科でせっかくキレイにしたお口の環境も、日常生活の中で悪習慣が続いてしまうと、残念ながら“台無し”になることがあります。
以下のNG行動は、なるべく控えるよう意識しましょう。
①ダラダラ食べ・ダラダラ飲み
特にジュース・スポーツ飲料・粘着性のあるお菓子などを時間を決めず食べることで糖分が長時間口の中に残り、むし歯菌の活動が活発化して、むし歯の原因となる酸を作り続けます。
口の中が常に酸性状態になり、エナメル質が溶けやすくなるため、せっかく予防処置をしても効果が低下してしまいます。
②就寝前に飲食する(特に糖質・酸性食品)
寝ている間は唾液量が一気に減少するため、自浄作用が働かず、むし歯リスクが最大化します。
また、歯周病菌も増える絶好の環境になります。
つまり、「夜食+就寝」は予防効果を大きく削る行為と言えます。
③歯磨きせずに寝る
これは、特に気を付けていただきたい項目です。
就寝中は、歯垢が最も成熟しやすいタイミングなので、細菌の増殖スピードは日中の約3〜5倍と言われます。
そのため、歯磨きをせず寝ることで、歯石形成や歯周病が進行して、PMTC・歯石取りの効果が無意味になってしまいます。
④強すぎるブラッシング圧
「ゴシゴシ強く磨く=キレイ」ではありません。
歯の表面が傷つき、着色や歯垢が付きやすくなるだけではなく、歯ぐきを傷つけ、退縮・知覚過敏の原因になります。
歯ブラシの圧力は、力を入れすぎず正しい角度で行うようにしましょう。
⑤研磨力の強い歯磨き粉を毎日使用
研磨剤の入った歯磨き粉を使用することで、歯の表面(エナメル質)に微細な傷がつき、逆に汚れが付着しやすくなります。
クリーニング後のツルツル維持を損なう行為になりますので注意してください。
⑦喫煙・加熱式タバコの吸引
喫煙を行うことで、
- 歯ぐきの血流低下
- 免疫力低下
- 組織の酸素不足
が起こり、歯周病リスクが上昇してしまいます。
せっかく歯石取りで炎症を減らしても、喫煙習慣で元通りになってしまいます。
⑧口呼吸
鼻呼吸ではなく、口呼吸を行うことで口内が乾燥し、細菌が増えてしまい歯ぐきの炎症、むし歯リスクが上昇します。
リスクが高まる行為になるので、口を閉じて鼻で呼吸する習慣をつけましょう。
⑨歯ぎしり・食いしばりを放置
歯ぎしり・食いしばりを放置することで、「歯がすり減り、むし歯になりやすい」や「エナメル質破損から起こる知覚過敏」などが起こる原因になってしまいます。
⑩噛み応えのある固い食品を頻繁に食べる
氷、あめ、スルメ、硬牡丹餅などを頻繁に食べることで、歯に負担がかかり、歯や詰め物・被せ物が欠けたりヒビ割れが起こる原因になります。
予防処置では対応できない「修復治療」が必要になりますので注意しましょう。
⑪歯間ブラシ・フロスをしない
歯ブラシのみでは歯と歯の間は磨けません。
歯と歯の間の汚れは歯周病やう蝕の原因の1つになります。
適切な器具を使用しお口の中を綺麗に保ちましょう。
⑫歯科医院へ半年以上行かない
セルフケアのみで歯科医院に定期検診に行ってない場合、無自覚で歯周炎が静かに進行している可能性があります。
初期の口腔内疾患は症状がでないことも多いので定期検診は行うようにしましょう。
おうちでできる予防歯科
予防歯科は歯医者だけで行うものではありません。
むしろ、日頃の習慣が“将来の歯の本数”を大きく左右します。
ここでは、おうちで簡単にできる予防方法をまとめて紹介します。
①適切な方法での歯磨き
適切な歯磨き方法で歯磨きをしましょう。
1日2~3回、特に寝る前は丁寧に
睡眠中は細菌が爆発的に増えるため、夜の歯磨きは最重要です。
毛先を歯と歯ぐきの境目に当てる「バス法」
むし歯と歯周病の両方の予防に最適です。
歯ブラシは“押す”のではなく“なでる”感覚で
優しく磨くと歯ぐきの退縮を防げます。
②フロスや歯間ブラシの併用
歯磨きだけでは約60%しか汚れが取れません。
歯と歯の間はむし歯の好発部位なので、1日1回以上は歯ブラシと併用するようにしましょう。
- フロス:歯と歯の間、狭い隙間向け
- 歯間ブラシ:広がった隙間に最適
③フッ素入りの歯磨き粉使用
フッ素はエナメル質を強化し、むし歯菌の酸に強くします。
1450ppm配合のもの(大人)を選ぶと効果的です。
④食生活のコントロール
お口の中に食べ物が長時間存在することで、う蝕や歯周病のリスクが上がってしまいます。
- ダラダラ食べをやめる
- 間食は時間を決める
- 糖質の多すぎに注意
- 酸性飲料の常飲を控える
など、口の中が中性に戻る時間を確保することが大切です。
⑤口呼吸を改善するトレーニング
鼻呼吸ではなく、お口を開けて呼吸してしまう方は要注意です。
口呼吸は口臭の原因や歯周病の悪化を引き起こします。
- 口テープ
- 舌の位置(上顎に付ける)
- 鼻呼吸練習
などの習慣をつけることをお勧めします。
⑥就寝中の歯ぎしり対策
歯ぎしり・食いしばりをすることで、顎や歯の痛みの原因になることが多いです。
- 寝る前のストレッチ
- カフェイン控えめ
- マッサージで筋緊張緩和
などを行い、歯ぎしりを予防する習慣をつけましょう。
⑦寝る前の間食をなくす
睡眠中は細菌が最も増殖して、むし歯・歯周病の原因になります。
食べたまま寝るのは絶対にやめましょう。
⑧禁煙・減煙
タバコは歯周病のリスクになります。
タバコを減らすことでリスクを下げることができます。
⑨定期的に歯ブラシを交換
毛先が広がると、汚れ除去率が下がってしまいます。
1〜1.5ヶ月での交換が目安です。
まとめ
むし歯や歯周病は、痛みが出てから治療するよりも、日常のお手入れで予防することが圧倒的に効率的です。
さらに、日常のお手入れにプラスして歯科医院での定期的なチェック・歯石取り・PMTCを組み合わせることで、「予防歯科」=一生、自分の歯で食べられる環境が実現します。
歯は一度失うと元には戻せません。
だからこそ、「おうちケア×プロケア」を両立させることが、未来の口腔健康の鍵。
今日からできる小さな予防習慣を、ぜひ一つずつ生活の中に取り入れてみてください。
あなたの何気ない毎日の習慣が、10年後、20年後の笑顔と食事の質を守ってくれます。