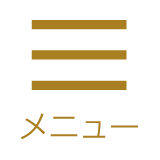歯医者で歯石取りはしないといけないの?しないとどうなる?

「定期的に歯石取りをしてください」と言われるけど、正直、痛いし面倒…という声はよくあります。
しかし、実は歯石取りを怠ると、お口の中では見えない病気が静かに進行します。
ここでは「なぜ必要なのか」「しないとどうなるのか」、そして歯医者が実際に行っている歯石除去の内容をわかりやすく解説します。
歯医者が行っている歯石取りとは?
歯医者が行う「歯石取り(スケーリング)」とは、歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットに付着した歯石を専用の器具で取り除く処置のことです。
セルフケアでは取れない“固まった汚れ”を除去し、歯周病や口臭を防ぐために非常に重要な治療です。
歯石とは
歯石は、歯垢(プラーク)が唾液中のカルシウム成分などと結合して硬くなったものです。
いったん歯石になると歯ブラシでは取れず、細菌の温床となり炎症や口臭の原因になります。
歯石取りの器具
歯科医院では主に以下の器具を使用します
| 方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 超音波スケーラー | 超音波振動で歯石を砕き水で洗浄 | 幅広い範囲を効率的に除去 |
| ハンドスケーラー | 手用器具で細かい歯石を削る | 仕上げや細部の調整に使用 |
| ルートプレーニング (根面清掃) |
歯周ポケット内部の歯石や汚れを取る | 中等度〜重度歯周病の治療に必要 |
歯石取りの方法
① スケーリング(歯ぐきの上の歯石除去)
歯の表面や歯ぐきの縁についた硬い歯石を、超音波スケーラー、手用スケーラーなどで細かく除去します。
② ルートプレーニング(歯ぐきの中についた歯石除去)
歯周ポケット内(見えない部分)にこびりついた歯石を丁寧に取り除き、歯根表面をツルツルに整えます。
③ 歯面研磨(PMTC)
専用のペーストやブラシで、歯の表面をツルツルに磨き上げます。
これにより、歯垢や着色がつきにくくなります。
なぜ歯石が溜まるのか?
歯石が溜まる理由は、歯垢(プラーク)が唾液の成分と反応して硬くなるためです。
歯垢は食べかすではなく、細菌のかたまり。
これが放置されると、唾液中のカルシウムやリンなどと結びつき、数日で石のように硬くなります。
歯石が溜まる仕組み(流れ)
- 食事・生活習慣で歯垢が付着
- 歯磨きが不十分 → 歯垢が残る
- 唾液のミネラルと結合
- 2〜3日で硬化(歯石化)
- 歯ブラシでは取れない → 蓄積・増加
なぜ歯石ができやすくなるのか?
以下の要因で歯石の形成スピードが上がります。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 磨き残し | 歯垢がとれず、固まる元に |
| 唾液の質・量 | ミネラルが多い人は歯石化しやすい |
| 食生活 | 甘い物・炭水化物が多いとプラーク増加 |
| 喫煙 | 唾液分泌や歯ぐきの免疫低下 |
| 口呼吸 | 口が乾くと細菌が増えやすい |
| 歯並びの乱れ | 磨きにくい部分にプラーク残留 |
| 加齢 | 唾液性状の変化、免疫低下 |
歯石取りをしないとどうなる?
歯石取りをしないで放置すると、歯周病が進行し、最終的には歯を失うリスクが高まります。
歯石は細菌の温床であり、炎症を引き起こし続けるため、口の健康に大きな悪影響を与えます。
歯石を取らないと起こること
①歯ぐきの炎症(歯肉炎)
「歯ぐきが赤く腫れる」「ブラッシングやフロスで出血しやすい」などの初期の歯周病のサインが起こります。
②歯周ポケットが深くなる
炎症により、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)が深くなり、そこにさらにプラーク・歯石がたまり炎症が悪化し、悪循環に陥る。
③歯周病が進行
歯を支える骨が溶けていく(歯槽骨吸収)、歯ぐきが下がり歯が長く見える、歯が揺れて噛みにくくなるなどの症状が顕著に現れてきます。
④口臭の原因に
歯石は細菌の塊 →は悪臭のガスを発生させます。
「口が臭う気がする…」という方は 歯石が大きな原因のことも多いです。
⑤歯が抜ける
歯周病が進むと支える骨がなくなり、自然に歯が抜けてしまいます。
⑥全身の健康にも影響
最近では歯周病が以下と関連すると言われています
- 心疾患・脳梗塞
- 糖尿病の悪化
- 誤嚥性肺炎
- 妊娠トラブル(早産など)
歯石取りは痛い?
歯ぐきに炎症が強い状態ほど痛みが出ます。
逆に、定期的に取っている人、炎症が少ない人はほど痛みはほぼありません。
つまり“定期歯石取り”は痛み予防にもなるということです。
理想的な歯石取りの頻度
理想的な歯石取りの頻度は、口腔内の状態によりますが一般的には3〜6ヶ月に1回です。
ただし、歯周病の有無や生活習慣によって適切な間隔は変化します。
なぜ3〜6ヶ月なのか?
- プラークが歯石になるのに約2〜3日
- 歯石周辺の細菌が歯周組織を壊し始める周期が約3ヶ月
- 歯周病が進行している人は細菌の増殖スピードが速い
つまり、歯石が付く前・病気が進む前に取るのがコツです。
理想的な頻度の目安
| 口腔状態 | 歯石取り頻度 | 理由 |
|---|---|---|
| 健康な歯ぐき (歯周病なし) |
6ヶ月に1回 | プラークの成熟と歯石形成を予防 |
| 軽度の歯周病 | 3〜4ヶ月に1回 | 炎症再発防止、ポケット内管理が必要 |
| 中〜重度歯周病 (メンテナンス期) |
1〜3ヶ月に1回 | 歯周ポケット内の細菌が増えやすい |
| 矯正治療中 | 3ヶ月に1回 | 装置で磨きにくく、汚れが溜まりやすい |
| インプラント治療後 | 3〜6ヶ月に1回 | インプラント周囲炎の予防が重要 |
| 喫煙者・糖尿病・ドライマウス | 3ヶ月に1回 | 歯周病リスクが高い |
歯石取りが上手な歯医者さんと歯石取りが上手ではない歯医者さんの違い
「上手な歯医者さん」と「そうでない歯医者さん」の違いは、単に歯石を取るだけでなく、歯ぐきや歯を守りながら、快適に・効果的にクリーニングできるかどうかです。
①丁寧で細部まで徹底している
歯と歯ぐきの境目、歯間、奥歯、裏側など見えにくい場所まで施術してくれる。
取り残しが少なく、 歯石が再付着しにくいため、適切な歯周管理が行えます。
②痛み・不快感が少ない
過度に力を入れない、部位によって超音波と手用器具を使い分ける、麻酔が必要な場合適切に対応など、症状、状態によって器具を使い分けます。
③ 歯ぐきや歯を傷つけない
歯の根面を削りすぎないことで、歯ぐきを切ってしまうリスクやしみやすさ、炎症悪化を防ぎます。
④口腔状況に合わせた施術
歯周病の有無、歯並び、被せ物の状態を見て対応、必要に応じて深い歯周ポケットの処置を行うことで効果が高く、治療計画が明確になります。
⑤セルフケア指導が的確
磨けていない箇所、フロス、歯間ブラシの使用方法などを把握することで日頃のブラッシングについても確認ができます。
自分で歯石取りをするのは危険
自分で歯石取りをするのは、とても危険です。
SNSや通販で「歯石取りキット」が人気ですが、歯科医師・歯科衛生士の立場から見れば、歯と歯ぐきを傷つけてしまうリスクが非常に高い行為です。
ここでは、そのリスクを詳しく解説します。
① 歯の表面に傷がつき、汚れが付きやすくなる
歯石取り用の器具には鋭い刃があります。
慣れていない方が使用すると、歯の表面(エナメル質)に細かい傷をつけてしまう原因になってしまいます。
その傷に歯垢や着色が入り込み、さらに歯石が付きやすい口腔状態へ悪化します。
② 歯ぐきを傷つけ、強い痛み・出血の原因に
歯石取りは歯ぐきギリギリのラインで、繊細な操作が必要です。歯ぐきは非常にデリケートな組織なので、誤って歯ぐきを切ってしまうと、
- 出血
- 腫れ
- 痛み
- 感染症
などのリスクが発生します。
③ 一番怖い“歯ぐきの中の歯石”は取れない
市販の器具で取れる歯石の多くは「見えている部分」だけです。
しかし、歯周病の原因となるのは歯ぐきの中(歯周ポケット)に付いた歯石。
セルフケアでは見えない部分にアプローチできず、本当に危険な歯石は残ったままになってしまいます。
④ 感染症のリスク
口の中には数百種類以上の細菌が存在します。
誤って傷をつけることで、細菌が血管へ侵入、炎症拡大、口臭悪化を引き起こす可能性があります。
⑤ 知覚過敏の原因になる
歯の表面を削ってしまうと、内部の象牙質が露出し、冷たいものや熱いもので「キーン!」と痛む知覚過敏が発生します。
⑥ 歯を支える歯根にダメージが出ることも
歯石取り用器具の角度・当て方を誤ると、
- 歯根面を削る
- 歯周組織を破壊
など、知らず知らずのうちに、歯を失うリスクを高める可能性があります。
⑦ 本来不要な部分まで削ってしまう危険
歯石と歯の境界は、プロである歯科医でも繊細な判断が必要になります。
そういったことがわからない一般の方がすると、
- 歯そのものを傷つける
- 歯根を削る
といったことになってしまう危険があります。
⑧ 効果“があるように見える”だけで根本解決にならない
SNSなどで「取れた」という情報があっても、実際には 歯石が残っていて菌が増殖し続けたり、再付着が早まったり、 病状進行が隠れてしまうなどの危険性があります。
専門的な診断なしでは、状態管理ができません。
おうちでできる歯石を溜まりにくくする方法
歯石は、歯垢(プラーク)が唾液中のカルシウムと結びついて固まった“細菌の塊”です。
一度できてしまうと歯ブラシでは落とせず、放置すると歯周病や口臭の原因になります。
しかし、普段の生活習慣で歯石を溜まりにくくすることは可能です。
今日からできる対策をご紹介します。
① 歯磨きは20〜30分以内に
食後の歯垢は、時間が経つほど成熟して固まりやすくなります。
特に就寝前は丁寧にブラッシングしてください。
② 歯ブラシだけでなく、フロスと歯間ブラシを併用
歯石は歯と歯の間にできやすいので、フロスを使うだけで歯垢除去率を上げることができます。
- フロス:歯と歯の隙間用
- 歯間ブラシ:歯ぐき下の広い隙間
③ バス法(45度の角度磨き)を意識
歯と歯ぐきの境目に毛先を当てる磨き方です。
歯石ができやすい部位の歯垢を効率的に除去できます。
④ 電動歯ブラシの導入
手磨きよりも安定して歯垢除去効果が期待できます。
「当てるだけ」で汚れを落としやすく、磨きムラを減らすことができます。
⑤ 研磨力の強い歯磨き粉の使いすぎに注意
歯の表面に傷がつくと、歯垢が付着しやすくなり歯石を助長します。
普段用は低研磨のものを選ぶのがおすすめです。
⑥ キシリトールガムで唾液量を増やす
唾液は“天然の洗浄液”。
ガムを噛むことで口腔内の環境が整い、歯垢の成熟を防ぎます。
⑦ 糖質の摂りすぎに気をつける
糖は細菌のエサになります。
おやつ・ジュースの頻回摂取は歯垢増加の大きな原因になります。
⑧ 水分摂取で口の中を乾燥させない
口が乾く(ドライマウス)と歯石増加リスクが上昇します。
意識してこまめに水分補給をするようにしてください。
⑨ 口呼吸の改善
口で呼吸をすると乾燥 → 歯垢が固まりやすくなります。
口テープや鼻炎治療も効果的です。
⑩ 喫煙を控える
ヤニ汚れで歯に凹凸ができ、歯垢が付着しやすくなります。
血流低下で歯ぐきの炎症も進行します。
まとめ
歯石は、日々の食事や生活で必ず溜まっていく細菌の塊です。
一度固まってしまうと、家庭での歯ブラシでは取り除くことができず、放置すると歯ぐきの炎症や歯周病、口臭の原因になってしまいます。
一見、ただの「お掃除」と思われがちな歯石取りですが、歯を失わないための予防医療として非常に重要な役割を担っています。
日常の習慣と定期ケアの両方をうまく組み合わせて、いつまでも健康な歯ぐきとキレイな笑顔を保ちましょう。